「今年で年賀状は最後にします」と伝える「年賀状じまい」。
日本の伝統的な新年の挨拶を終える決断は、少し寂しさを伴うものです。
しかし、郵便料金の値上げやデジタル化、環境配慮の流れから、2026年にかけて年賀状じまいを選ぶ人や企業は確実に増えています。
大切なのは、ただやめるのではなく「感謝」と「これからもつながりたい気持ち」を添えて丁寧に伝えること。
本記事では、年賀状じまいの最新事情から、相手に失礼のない伝え方、さらに友人・親族・ビジネス相手などシチュエーション別の豊富な文例まで網羅しています。
フルバージョンの例文を参考にすれば、そのまま使える安心の文章が見つかります。
「どう書けばいいか分からない」と悩んでいる方に役立つ、2026年版の完全ガイドです。
年賀状じまいとは?2026年の最新事情
ここでは「年賀状じまい」という言葉の意味と、2026年にどんな動きがあるのかを整理します。
最近ニュースや雑誌で耳にする機会も増えてきましたが、改めて確認しておきましょう。
年賀状じまいの定義と意味
「年賀状じまい」とは、長年続けてきた年賀状のやりとりを一区切りとし、相手にその旨を伝えることを指します。
単純に送らなくなることとは異なり、「今後は年賀状を控えますが、感謝の気持ちとお付き合いは続けたい」と伝えるのが特徴です。
こうすることで、相手に不安や誤解を与えず、円満に関係を続けることができます。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 年賀状じまい | 今後は年賀状を出さないと伝える挨拶 |
| 終活年賀状 | 人生の節目や終活の一環として行う年賀状じまい |
| 年賀欠礼 | 喪中など特別な事情で年賀状を出さないこと |
2026年に増える背景(社会・文化・デジタル化)
2026年の年賀状じまいが注目される背景には、社会的な変化があります。
まず、郵便料金の値上げにより年賀状1枚あたりのコスト負担が大きくなったこと。
さらに、LINEやメールなどのデジタルツールの普及で、紙にこだわらない挨拶が増えてきました。
環境意識(SDGs)も大きな要因です。
「紙を減らすことで環境にやさしい」という理由から、企業や若い世代を中心に年賀状じまいが広がっています。
| 背景要因 | 具体例 |
|---|---|
| 郵便料金の上昇 | 2024年に63円→85円へ値上げ |
| デジタル化 | メールやSNSでの新年挨拶が一般化 |
| 高齢化・終活 | 70代以上を中心に「筆を持つのが大変」との声 |
| 環境配慮 | 企業が「紙資源削減」を理由に廃止 |
つまり、2026年の年賀状じまいは個人の事情だけでなく、社会全体のトレンドとして拡大しているのです。
年賀状じまいを考えるきっかけとメリット・デメリット
この章では、なぜ人々が年賀状じまいを考えるようになったのか、そしてメリットとデメリットを整理します。
「やめたいけど寂しい気もする…」という揺れる気持ちを整理するのに役立つはずです。
よくあるきっかけ(高齢化・終活・ライフスタイルの変化)
年賀状じまいの理由は人によってさまざまですが、よくあるきっかけを見てみましょう。
高齢化や終活を理由にする方は多く、年齢を重ねて「筆を取るのが大変」と感じることがあります。
また、ライフスタイルの変化も大きな要因です。
たとえば、仕事が忙しく年末に余裕がない、子どもが成長して写真付き年賀状をやめる、転職や引越しで人間関係が変わるなど。
「区切り」として年賀状じまいを選ぶケースが増えているのです。
| きっかけ | 具体的な例 |
|---|---|
| 高齢化 | 筆をとるのがつらい、目が疲れる |
| 終活 | 人生の整理の一環として |
| ライフスタイルの変化 | 転職・退職、子どもの独立、引越し |
| 時代の流れ | SNSやLINEなどデジタル手段への移行 |
年賀状じまいのメリット(時間・費用・人間関係の整理)
年賀状じまいには多くのメリットがあります。
まず時間と費用の節約。
特に2024年にハガキ代が85円に値上がりしたため、100枚出せば8,500円。
印刷代やインク代を含めればさらにかかります。
また、作業にかかる数時間〜数日は大きな負担です。
さらに、人間関係を見直すきっかけになるという声もあります。
「毎年年賀状だけのやり取りになっていた相手」との関係を整理できるのです。
| メリット | 効果 |
|---|---|
| 時間の節約 | 宛名書き・投函の手間が不要 |
| 費用の削減 | はがき代・印刷代・インク代が不要 |
| 人間関係の整理 | 惰性で続いていた関係を見直せる |
| 環境への配慮 | 紙資源を削減できる |
年賀状じまいのデメリット(誤解・寂しさ・再開しづらさ)
一方で、デメリットも存在します。
代表的なのは「失礼に思われるリスク」です。
年賀状を大事にしている方からすると、突然の辞退は「関係を切られた」と感じられることも。
また、翌年以降のお正月に届く年賀状が減り、少し寂しく感じることもあります。
さらに、いったん辞めたあと「やっぱり復活したい」と思ったときに再開しづらいのも難点です。
| デメリット | 注意点 |
|---|---|
| 失礼に思われる可能性 | 一方的だと「絶縁」と誤解されることも |
| お正月が寂しい | 年賀状の楽しみがなくなる |
| 再開しにくい | 「前に辞退したのに」と気まずさが残る |
メリットとデメリットを理解したうえで決断することが、後悔しない年賀状じまいの第一歩です。
年賀状じまいを伝える正しいタイミングと方法
この章では、年賀状じまいを「いつ」「どのように」伝えるのが良いのかを解説します。
突然やめるのではなく、相手に配慮した伝え方を知っておきましょう。
年賀状で伝える場合(最後の1枚に添える)
もっとも一般的な方法は最後の年賀状に「今年をもって最後にします」と添えることです。
「これまでのお礼」と「今後もお付き合いを続けたい気持ち」を一緒に書き加えると、相手に安心感を与えます。
「来年からやめます」と事前に知らせることがマナーなのです。
| 伝え方 | ポイント |
|---|---|
| 最後の年賀状に書き添える | もっとも自然で丁寧な方法 |
| 文末に一言添える | 「本年をもちまして年賀状は失礼させていただきます」など |
寒中見舞いや喪中はがきで伝えるケース
年賀状で伝えるのに抵抗がある場合は、寒中見舞いや喪中はがきで年賀状じまいを知らせる方法もあります。
寒中見舞いは松の内(1月7日頃)が明けたあとから立春までに出す挨拶状。
新年の喜ばしい雰囲気を避けたいときに適しています。
喪中はがきに合わせて伝えるケースもありますが、「喪中」と「年賀状じまい」を一緒に伝えるのは不快に感じる人もいるため注意が必要です。
| 方法 | 適した状況 |
|---|---|
| 寒中見舞い | 新年にネガティブな話題を避けたい場合 |
| 喪中はがき | 喪中で年賀状を出せない年に合わせる場合 |
メールやSNS・直接伝える場合の注意点
友人や同僚など、気心が知れた相手にはメールやLINE、SNSのDMで伝えても問題ありません。
ただし、一斉送信すると冷たい印象になるので、一人ひとりに合わせた言葉を添えると良いでしょう。
直接会う機会がある相手には、口頭で伝えるのも誤解が少なくおすすめです。
表情や声のトーンで気持ちが伝わるため、特に年配の方やお世話になった方には安心して受け入れられやすい方法です。
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| メール・SNS | 手軽に伝えられる | 一斉送信は避ける |
| 直接伝える | 誤解が少ない、気持ちが伝わりやすい | 会う機会がある相手に限定される |
まとめると、相手との関係性に応じて伝える手段を選ぶことが、円満な年賀状じまいのコツです。
年賀状じまいの書き方とマナー
この章では、年賀状じまいを失礼なく伝えるための「基本構成」と「マナーの工夫」を解説します。
実際の文面を考える前に、まずは型を押さえておきましょう。
基本構成(新年挨拶・感謝・辞退理由・今後のつながり)
年賀状じまいの文章は、大きく4つのパートに分けると自然です。
それぞれが欠けると不自然になったり、相手に誤解を与えやすくなります。
| 構成要素 | 例文イメージ |
|---|---|
| ①新年の挨拶 | 「あけましておめでとうございます」など |
| ②感謝の気持ち | 「長年のご厚情に心より感謝申し上げます」 |
| ③辞退の理由 | 「高齢となり筆をとるのが難しくなりました」 |
| ④今後のつながり | 「これからも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます」 |
この4ステップを意識するだけで、どんな相手にも失礼のない文面が作れます。
年代別の書き方の工夫(20代〜80代まで)
同じ「年賀状じまい」でも、年代によって適した理由や表現は異なります。
例えば20代なら「時代の流れや環境配慮」を理由に、70代なら「高齢や終活」を理由にすると受け入れられやすいのです。
| 年代 | よくある理由 | 文面の工夫 |
|---|---|---|
| 20代〜30代 | デジタル化・環境意識 | 「今後はSNSやメールでやり取りできれば幸いです」 |
| 40代〜50代 | 子どもの成長・ライフスタイル変化 | 「子どもも成人したため、年賀状は区切りといたします」 |
| 60代 | 退職・定年 | 「定年退職を機に年賀状を控えさせていただきます」 |
| 70代〜80代 | 高齢・終活 | 「寄る年波を感じ、筆をとるのも難しくなりました」 |
相手別の書き方(友人・親族・上司・取引先など)
送る相手によっても、言葉遣いやトーンを変える必要があります。
友人にはカジュアルに、上司や取引先にはフォーマルにという切り替えが大切です。
| 相手 | 表現のポイント |
|---|---|
| 友人・知人 | 「これからはLINEでやり取りできたらうれしいです」など柔らかく |
| 親族 | 「高齢のため年賀状は失礼いたしますが、電話で近況を伝えます」 |
| 上司・同僚 | 「勝手ながら、本年をもって年賀状は控えさせていただきます」 |
| 取引先 | 「環境配慮とデジタル化推進のため、来年より年賀状を控えます」 |
注意点として、相手に誤解されないよう「絶縁ではなく、今後もお付き合いを続けたい」意思を必ず添えることが重要です。
2026年向け・シチュエーション別年賀状じまい文例集
ここでは、実際に使える「年賀状じまい」の具体的な文例を紹介します。
フォーマルからカジュアルまで、シチュエーションに合わせた文章を参考にしてください。
フォーマルに伝える一般的な文例
まずはオーソドックスな形です。
目上の方や親戚、幅広い相手に対応できる文面です。
あけましておめでとうございます。
これまで長らく年賀状でのご挨拶をいただき、心より感謝申し上げます。
誠に勝手ながら、本年をもちまして年賀状による新年のご挨拶を終えさせていただきます。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
高齢・終活を理由にした文例
年齢を理由にすると、相手も自然に受け止めてくれます。
あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
私も高齢となり、筆をとるのが難しくなってまいりました。
誠に勝手ではございますが、今年をもちまして年賀状は失礼させていただきます。
今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。
仕事関係・ビジネスで使える文例
企業や取引先に向けては、理由を「業務効率化」や「環境配慮」にするとスマートです。
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
平素より格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に恐縮ではございますが、弊社では業務効率化ならびに環境配慮の観点から、来年より年賀状によるご挨拶を控えさせていただくこととなりました。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
友人や知人に送るカジュアルな文例
気心の知れた友人には、少しくだけた言葉でOKです。
あけましておめでとう!
これまで年賀状でご挨拶できてうれしかったです。
勝手ながら、来年からは年賀状を送らないことにしました。
これからはLINEやメールで近況をやりとりできればうれしいです。
今年もよろしくね。
メールやLINEで伝える文例
紙の年賀状ではなく、デジタルで伝える場合の文例です。
こんにちは。
少し早いですが、ご連絡させていただきます。
誠に恐縮ですが、来年以降は年賀状でのご挨拶を控えさせていただくことにしました。
これからもメールやLINEで、変わらず近況をやりとりできれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
体調や多忙を理由にした文例
体調や仕事の忙しさを理由にするのも自然です。
新しい年が皆さまにとって健やかな一年となりますよう、お祈り申し上げます。
近年は健康上の都合や多忙のため、年賀状の作成が難しくなってまいりました。
誠に勝手ではございますが、今年限りで年賀状でのご挨拶は控えさせていただきます。
これまでの温かいお心遣いに心より感謝いたします。
| シチュエーション | 文例の特徴 |
|---|---|
| フォーマル | 幅広い相手に使える無難な定型 |
| 高齢・終活 | 自然で納得感がある |
| ビジネス | 環境配慮・業務効率化を理由に |
| 友人 | カジュアルで温かみのある表現 |
| メール・LINE | 簡潔で柔らかい表現 |
| 体調・多忙 | 無理をせず丁寧に断る |
自分の状況に合った文例を選び、心を込めて伝えることが、円満な年賀状じまいの秘訣です。
年賀状じまいを後悔しないためのコツ
「やっぱりやめなければよかった」とならないためには、あらかじめ注意点を知っておくことが大切です。
ここでは、よくある後悔と、それを防ぐ工夫を紹介します。
ありがちな後悔パターン
年賀状じまいをした人からは、次のような後悔の声も聞かれます。
- 事前に伝えずにやめてしまい、相手に誤解や心配をかけた
- お正月に年賀状が届かず、寂しさを感じた
- 数年後に「やっぱり復活したい」と思っても言い出しにくい
「黙ってやめる」のはNGであり、最も後悔につながるパターンです。
円満に伝えるための工夫
後悔を避けるには、伝え方にひと工夫を加えることが重要です。
とくに大切なのは「感謝」と「今後もつながりたい意思」を必ず添えることです。
| 工夫 | 効果 |
|---|---|
| 感謝を伝える | 「これまで本当にありがとうございました」で印象アップ |
| 今後のつながり方を示す | 「これからはLINEで近況を」など代替手段を提示 |
| 相手ごとに表現を変える | 親しい人にはカジュアル、上司にはフォーマル |
相手の立場を考えて言葉を選ぶことが、誤解や寂しさを防ぐ最大のポイントです。
年賀状じまい後の新しいつながり方
年賀状をやめても、関係が終わるわけではありません。
むしろ、別の形で新しい交流が生まれることもあります。
たとえば、年明けに「あけおめLINE」を送り合う、SNSでお正月の写真をシェアするなど。
誕生日や記念日にメッセージを送るのも、以前より距離が縮まるきっかけになるかもしれません。
| 手段 | 活用法 |
|---|---|
| LINE・メール | 手軽に近況を伝え合える |
| SNS | 写真やコメントで交流を継続 |
| 電話 | 大切な相手には声で伝えると温かみがある |
| 季節の挨拶 | 暑中見舞いや年末のご挨拶に切り替える |
「年賀状じまい」=人間関係じまいではないと考え、無理のない方法で交流を続けていきましょう。
まとめ|2026年の年賀状じまいは丁寧な一言がカギ
ここまで「年賀状じまい」の背景やマナー、文例を紹介してきました。
最後に、要点を整理しておきましょう。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 背景 | 高齢化・終活・郵便料金の値上げ・デジタル化・環境配慮 |
| 基本構成 | ①新年挨拶 ②感謝 ③辞退理由 ④今後のつながり |
| 伝え方 | 最後の年賀状に添える、寒中見舞い、メールや直接伝える |
| 後悔を防ぐコツ | 感謝を忘れない、代替手段を提示、相手に合わせた表現 |
2026年の年賀状じまいは、時代の流れに沿った自然な選択肢です。
ただし、長年続けてきた習慣をやめることは、相手にとっても大きな変化。
「感謝」と「これからもつながりたい」という気持ちを必ず添えることが、円満に伝えるための秘訣です。
紹介した文例を参考に、自分らしい言葉で丁寧に伝えてみてください。
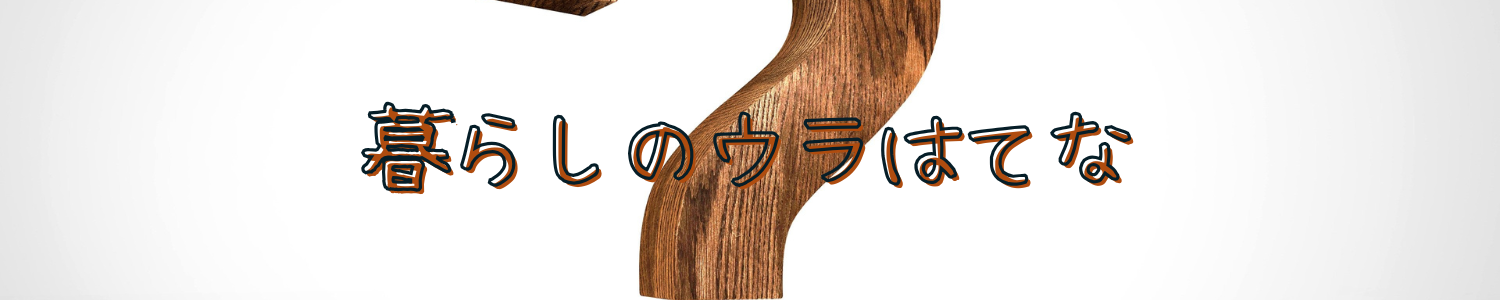
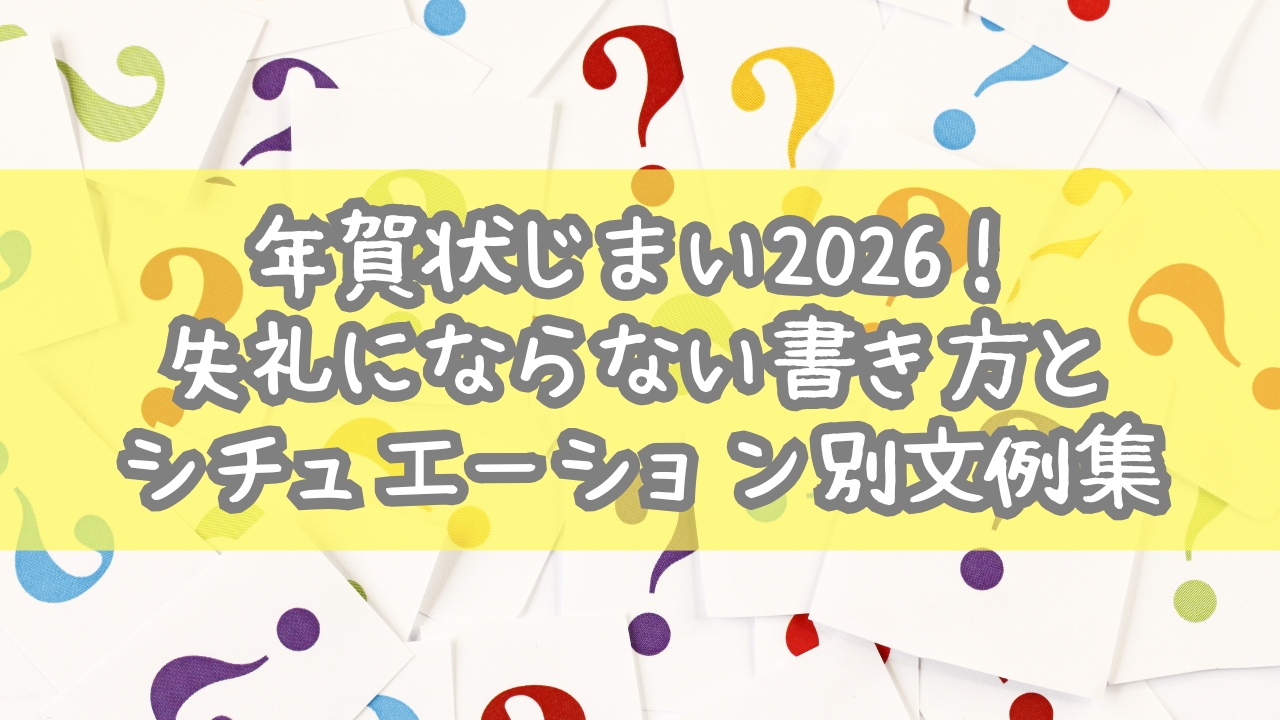
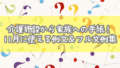
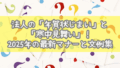
コメント