年末のご挨拶として贈るお歳暮は、ただ品物を送るだけではなく、心を込めた送り状を添えることでより丁寧な印象を与えられます。
送り状には、日頃の感謝の気持ちや来年への願いを言葉にして伝える役割があります。
しかし「どんな言葉を書けばよいのか」「相手によって表現を変えるべきか」と迷う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、お歳暮の送り状の基本的な書き方から、目上の方・取引先・友人など相手別に使える例文までをわかりやすく解説しました。
さらに、送り状を添える際のマナーや、より丁寧に伝えるための工夫、よくある疑問点についても詳しく紹介しています。
この記事を読めば、送り状の作成で迷うことなく、自信を持って相手に感謝を伝えることができます。
お歳暮の送り状とは?基本の意味と役割
お歳暮の送り状とは、贈り物を相手に送る際に添える手紙のことです。
単に品物を送るだけでなく、文章にして感謝やご挨拶を伝えることで、より丁寧な印象を与える役割を果たします。
送り状は「贈る心」を形にする大切なマナーといえます。
送り状と添え状の違い
お歳暮には「送り状」と「添え状」という似た言葉があります。
送り状は、贈り物とは別に郵送する手紙を指します。
一方、添え状は贈り物に同封する短いメッセージカードや簡単な書面を意味します。
つまり、送り状はより正式で文章量が多い手紙、添え状は簡潔な添え書きという違いがあります。
| 種類 | 送る方法 | 文章の長さ | 使用シーン |
|---|---|---|---|
| 送り状 | 別送(郵送など) | やや長め | 目上の方やビジネス関係 |
| 添え状 | 品物に同封 | 短め | 親しい関係やカジュアルな場面 |
お歳暮に送り状を添える理由
送り状を添えることには、相手への敬意をきちんと伝える意味があります。
「感謝の気持ちを文章にする」ことは、相手にとって忘れにくい印象を残します。
特に、ビジネスや目上の方へのお歳暮では、送り状の有無が信頼感や礼儀正しさに直結します。
形式ばった印象にならないように、柔らかい言葉を交えると読みやすくなります。
送り状は、贈り物の価値をさらに高める「言葉の贈り物」といえるでしょう。
お歳暮の送り状の基本的な書き方
お歳暮の送り状は、決まった流れに沿って書くことで読みやすく、相手に誠意が伝わります。
基本は「時候の挨拶 → 感謝の言葉 → 贈り物を送ったことの報告 → 結びの言葉 → 日付と署名」という順序です。
この流れを押さえるだけで、誰でも丁寧な送り状を書けるようになります。
冒頭の時候の挨拶の例
書き出しには、季節感や相手を気遣う言葉を入れるのが一般的です。
たとえば12月なら「師走の候」「歳末の候」などがよく使われます。
例文:「拝啓 師走の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。」
堅苦しくなりすぎないように、相手との関係性に合わせて調整することが大切です。
| 季節の挨拶の例 | 使える時期 |
|---|---|
| 師走の候 | 12月全般 |
| 歳末の候 | 12月後半 |
| 寒冷の候 | 12月〜2月 |
感謝の気持ちと贈り物の説明
本文では、今年お世話になったことへの感謝を述べます。
そして、心ばかりのお歳暮をお送りしたことを伝えましょう。
例文:「本年も格別のご厚情を賜り、心より感謝申し上げます。ささやかではございますが、お歳暮の品をお送りいたしました。」
贈り物の具体的な中身を細かく書く必要はありません。
「気持ちを込めて選んだ」というニュアンスを添えると、より丁寧な印象になります。
結びの言葉と署名のルール
結びでは、相手の幸せや良い新年を願う言葉を添えて締めくくります。
例文:「厳しい寒さが続きますが、どうぞお体を大切にお過ごしください。来たる年も幸多き一年となりますようお祈り申し上げます。」
最後に日付を書き、自分の名前を署名します。
ビジネスの場合は、会社名と担当者名を記すのが一般的です。
署名を忘れると、送り主がわからず失礼になるので注意が必要です。
| 要素 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 日付 | 和暦でも西暦でも可。年号+月日を明記。 |
| 署名 | フルネームで書く。ビジネスは会社名+役職+氏名。 |
| 敬具 | 「拝啓」で始めた場合は必ず「敬具」で締める。 |
基本の構成を守るだけで、形式を重んじる相手にも安心して届けられる送り状になります。
お歳暮の送り状の例文集(相手別)
送り状は相手との関係性に合わせて書き方を工夫することが大切です。
ここでは「目上の方」「取引先・ビジネス関係者」「親しい友人や親戚」「カジュアルな関係」の4つの例文を紹介します。
自分の立場に合った表現を選べば、形式に迷わず書けるようになります。
目上の方・恩師への例文
拝啓 師走の候、〇〇様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
本年も大変お世話になりましたこと、心より厚く御礼申し上げます。
ささやかではございますが、お歳暮の品をお送りいたしました。
ご笑納いただければ幸いに存じます。
寒さ厳しき折、どうぞご自愛のほどお願い申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日
〇〇(送り主名)
取引先・ビジネス関係者への例文
拝啓 歳末の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
本年のご厚情に感謝を込め、心ばかりのお歳暮をお送りいたしました。
ご笑納いただければ幸いでございます。
来年も変わらぬご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日
〇〇株式会社
〇〇部 〇〇(担当者名)
親しい友人や親戚への例文
拝啓 冬の寒さが身にしみる季節となりました。
〇〇さんにはお変わりなくお過ごしでしょうか。
今年も大変お世話になりましたので、感謝の気持ちを込めてお歳暮をお送りします。
気に入っていただければうれしいです。
寒さが続きますので、どうぞ温かくしてお過ごしください。
令和〇年〇月〇日
〇〇(送り主名)
カジュアルな関係でも失礼にならない例文
拝啓 年の瀬も押し迫ってまいりました。
今年も仲良くしてくださり、本当にありがとうございました。
感謝の気持ちとして、お歳暮を送ります。
どうかお気軽に受け取っていただければ幸いです。
来年も楽しい時間を共有できますように。
令和〇年〇月〇日
〇〇(送り主名)
| 相手 | 文体の特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 目上の方 | 丁寧で格式を重んじた言葉 | 敬語を崩さない |
| 取引先 | ビジネス的で簡潔 | 会社名・部署名を明記 |
| 友人・親戚 | 親しみを込めた表現 | 堅すぎない文章 |
| カジュアル | 柔らかくフランクな表現 | くだけすぎない程度に調整 |
例文をベースにアレンジすれば、自分らしい言葉で送り状を書くことができます。
送り状を添える際のマナーと注意点
送り状は形式だけでなく、送るタイミングや表記方法などにも気を配る必要があります。
ここでは、よくある疑問点や注意点を整理しました。
マナーを押さえることで、相手に安心感と誠意を伝えられます。
手書きとパソコン作成の違い
送り状は必ずしも手書きである必要はありません。
最近はパソコンで作成し、印刷した送り状を使う方も増えています。
大切なのは文字の形式ではなく、感謝の気持ちがしっかりと伝わるかどうかです。
字に自信がある方は手書きにすると温かみが増し、読みやすさを重視するなら印刷が便利です。
| 作成方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 手書き | 気持ちが伝わりやすい | 字の読みやすさに注意 |
| パソコン印刷 | 整った見た目で誰でも読みやすい | 冷たい印象にならないよう言葉選びに配慮 |
送り状を送るタイミング
送り状はお歳暮の品物が届く前後に送るのが一般的です。
品物が到着する前に送り状が届くと、より丁寧な印象を与えられます。
ただし、遅くなりすぎると年始の挨拶と混同されることもあるため注意が必要です。
12月上旬から20日ごろまでに届くように送るのが安心です。
会社名・代表者名・連名の表記方法
ビジネスの場合は会社名、部署名、担当者名を明記するのがマナーです。
個人の場合はフルネームを記載し、家族や夫婦連名で送ることも可能です。
署名が不十分だと、相手に「誰から届いたのか分からない」という誤解を与えてしまうので要注意です。
| 状況 | 署名の書き方 |
|---|---|
| ビジネス | 会社名+部署名+担当者名 |
| 個人 | フルネーム |
| 夫婦 | 夫婦連名(例:山田太郎・花子) |
形式を整えることで、相手に安心して受け取ってもらえる送り状になります。
より丁寧に伝わる送り状の工夫
基本的な書き方を守るだけでも十分ですが、少しの工夫を加えることで送り状はさらに印象的になります。
ここでは、便箋や封筒の選び方、言葉の工夫、贈り物と一緒に送る際の配慮について解説します。
「心を込めて書いた」と伝わる小さな工夫が、相手との信頼を深めるきっかけになります。
便箋・封筒の選び方とマナー
送り状に使用する便箋や封筒は、シンプルで落ち着いたデザインを選ぶのが無難です。
柄や色が派手すぎると、ビジネスや目上の方にはふさわしくない場合があります。
白や淡い色合いの便箋、無地の封筒を用いると安心です。
華美なデザインは避け、清潔感を重視しましょう。
| アイテム | おすすめの選び方 |
|---|---|
| 便箋 | 白や淡い色、罫線入りで書きやすいもの |
| 封筒 | 無地、二重封筒がより丁寧 |
柔らかい表現を加える言葉のヒント
送り状の文章は形式を重んじつつも、堅苦しくなりすぎないようにすると温かみが伝わります。
例えば「ご笑納ください」という表現は、「どうぞお気軽にお受け取りください」といった柔らかい言葉に言い換えることも可能です。
また、「寒さ厳しき折」という言い回しを「冷え込む日が続いておりますが」と変えると親しみが増します。
相手の立場を思い浮かべて、言葉を少し調整するだけで印象が大きく変わります。
お歳暮に同封する場合の注意点
本来、送り状は別送が基本ですが、贈り物に同封しても失礼ではありません。
ただし、その場合は添え状に近い形で簡潔にまとめると良いでしょう。
また、同封する場合は品物が傷つかないように、便箋を折って封筒に入れるか、クリアファイルに挟むなどの工夫も必要です。
文章が長すぎると読み手に負担を与えるので、簡潔にまとめることを意識しましょう。
| ケース | 送り状の書き方 |
|---|---|
| 別送 | 正式な書式で、時候の挨拶から結びまでしっかり記載 |
| 同封 | 簡潔にまとめ、相手に気持ちを伝える短文 |
工夫を少し加えるだけで、送り状は「形式的な手紙」から「心を込めた贈り物」へと変わります。
お歳暮の送り状でよくある質問(FAQ)
送り状を書く際には、細かい場面で迷うことも多いですよね。
ここでは、よくある質問をまとめて解説します。
疑問点を解消してから送り状を用意すれば、安心して相手に届けられます。
送り状を忘れたときの対応
もし送り状を同封し忘れてしまった場合でも、後から別送すれば問題ありません。
その際には「先日お送りしましたお歳暮に送り状を添えそびれてしまいました」とひと言添えると丁寧です。
そのままにせず、必ずフォローの手紙を送ることが大切です。
メールやLINEで代用できる?
近年はメールやLINEなどのデジタルツールで感謝の気持ちを伝える方も増えています。
ただし、ビジネスや目上の方には正式な送り状を送るほうが安心です。
親しい友人やカジュアルな関係なら、メールで一言添える形でも問題ありません。
相手との関係性に合わせて使い分けるのがポイントです。
喪中の相手に送るときの注意点
相手が喪中の場合でも、お歳暮を贈ること自体は失礼には当たりません。
ただし送り状の中で「お祝い」という言葉は避け、落ち着いた表現を選ぶことが望ましいです。
例えば「ご自愛ください」「良き年をお迎えください」といった言葉に置き換えると安心です。
相手の状況を思いやり、控えめな表現を意識することが大切です。
| シーン | 対応の仕方 |
|---|---|
| 送り状を忘れた | 後から別送し、ひと言お詫びを添える |
| メールやLINE | カジュアルな関係では可、ビジネスでは不可 |
| 喪中の相手 | 「お祝い」などの表現を避け、落ち着いた文章に |
よくある疑問に備えておけば、失礼のない送り状を安心して送ることができます。
まとめ
お歳暮の送り状は、単なる形式ではなく感謝の気持ちを形にする大切な手段です。
基本の構成「時候の挨拶 → 感謝の言葉 → 贈り物の報告 → 結び → 日付と署名」を押さえれば、誰でも安心して書くことができます。
また、相手に応じた例文や表現を参考にすることで、状況に合わせた適切な送り状を作成できます。
送り状は「心を届けるもう一つの贈り物」です。
今年はぜひ、お歳暮と一緒に送り状を添えて、日頃の感謝を言葉にして伝えてみてください。
きっと相手との関係がより深まり、心のこもった交流へとつながっていきます。
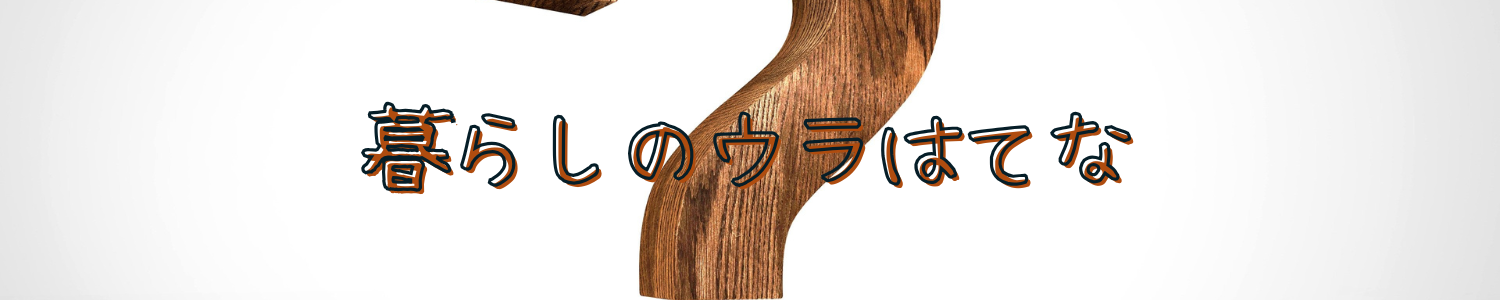
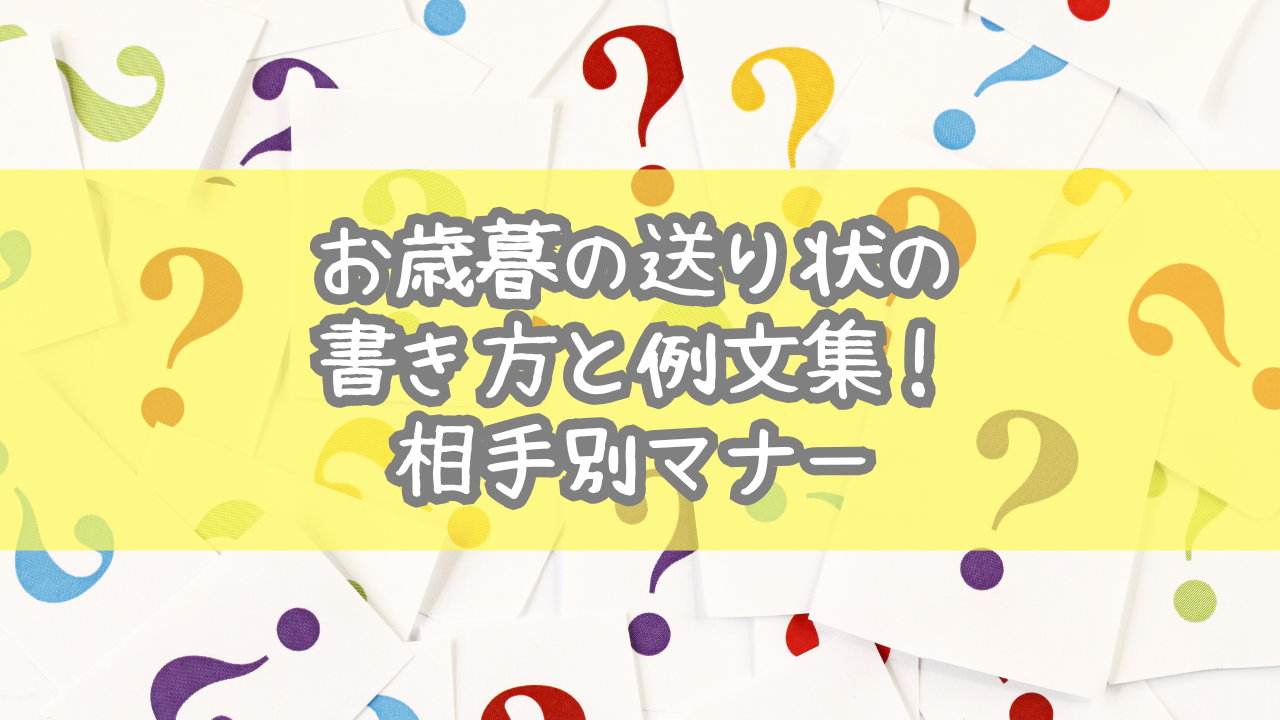
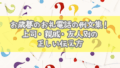
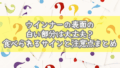
コメント