新しい年のご挨拶といえば年賀状――そう考える方も多いですが、法人の間では「年賀状じまい」という新しい動きが広がっています。
背景には、郵便料金の値上げやペーパーレス化、SDGsへの配慮といった社会的要請があります。
しかし「挨拶をやめる=関係を終える」わけではありません。
むしろ、最近では年賀状に代わる丁寧なご挨拶として「寒中見舞い」を活用する法人が増えているのです。
本記事では、法人が「年賀状じまい」を進める際に押さえておきたいポイントや、「寒中見舞い」を効果的に活用する方法を解説します。
送る時期の目安からビジネス文例、取引先への配慮まで、2025年の最新事情を網羅。
この記事を読めば、法人としてスマートかつ誠意ある挨拶の形が見つかります。
法人における「寒中見舞い」と「年賀状じまい」が注目される背景
ここでは、なぜ法人の間で「年賀状じまい」と「寒中見舞い」が注目されているのかを整理します。
社会の変化やビジネスマナーの進化を背景に、これらの習慣が見直されている理由を具体的に見ていきましょう。
年賀状じまいが広がる社会的・経済的理由
法人が「年賀状じまい」を選ぶ背景には、いくつかの社会的・経済的な事情があります。
代表的な要因としては、郵便料金の値上げや、紙やインク代といったコストの増加が挙げられます。
また、近年のペーパーレス化やSDGs(持続可能な開発目標)への意識の高まりも大きな要因です。
さらに、企業の働き方改革やリモートワークの普及により、従来型の一斉印刷・発送が負担になってきたことも背景にあります。
| 背景要因 | 具体的内容 |
|---|---|
| コスト面 | 郵便料金値上げ、印刷費、事務作業の人件費 |
| 社会的要請 | ペーパーレス化、環境意識、SDGs |
| 働き方の変化 | リモートワーク、業務効率化の必要性 |
「年賀状じまい」は単なる節約ではなく、社会的責任や効率化の一環として進んでいるのです。
法人間のビジネス慣習としての変化
以前は、年賀状が取引先との「信頼の証」とされていました。
しかし、現在はメールやSNS、WEB挨拶状といったデジタル手段が浸透し、必ずしも紙の年賀状でなければならないという意識は薄れています。
特に若い世代の経営者や担当者は、スピード感を重視する傾向が強く、デジタル挨拶への移行に前向きです。
こうした背景から、「年賀状をやめること=関係を絶つこと」ではなく、「新しい形のコミュニケーションに切り替えること」として受け入れられつつあります。
なぜ寒中見舞いが代替手段として選ばれるのか
「年賀状じまい」をした後も、法人にとって「ご挨拶」を続けることは重要です。
そこで選ばれるのが寒中見舞いです。
寒中見舞いは、新年の慌ただしい時期を避けて出せるため、相手にじっくりと気持ちを伝えられる点が好まれます。
また、喪中や体調不良などで年賀状を出せなかった場合のお詫びとしても適しているため、柔軟性が高いのが特徴です。
| 寒中見舞いのメリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 送る時期の余裕 | 1月8日〜2月初旬まで対応可能 |
| ビジネスマナー | お詫び・感謝・配慮を伝えやすい |
| 柔軟性 | 年賀状の代替、喪中時の対応にも活用可 |
法人にとって寒中見舞いは、年賀状じまい後の「新しいビジネス挨拶ツール」として位置づけられているのです。
法人が押さえるべき「寒中見舞い」の基本マナー
法人として寒中見舞いを送る場合には、一般的なマナーに加えて、ビジネスならではの配慮が求められます。
ここでは、送る時期、注意すべきマナー、そして紙とデジタルの選び方を整理してご紹介します。
寒中見舞いを出す時期とタイミング(2025年最新版)
寒中見舞いを出すのは、松の内(一般的に1月7日まで)が明けてから立春(2月3日)の前日までが目安です。
つまり、2025年の場合は1月8日〜2月2日までに先方へ届くように準備しましょう。
地域によって「松の内」を1月15日とするところもありますが、この範囲を守れば大きな失礼にはなりません。
| 期間 | 送付可能な挨拶 |
|---|---|
| 1月1日〜1月7日 | 年賀状 |
| 1月8日〜2月3日 | 寒中見舞い |
| 2月4日以降 | 余寒見舞い |
「いつ送ればいい?」という迷いは、この表を基準にすれば一目で解決します。
法人ならではの配慮ポイント
法人として送る寒中見舞いでは、個人用とは異なる注意点があります。
特に相手企業との信頼関係を意識した内容にすることが大切です。
- 社名・役職・氏名を正確に記載する
- 会社や部署の近況を簡潔に添える
- 年賀状の代替で送る場合は「お詫び+感謝」を忘れない
- 取引先の状況(喪中など)に十分配慮する
例えば「この度は年賀状をお控えになられたと伺いました」と一言添えるだけで、相手への心遣いが伝わります。
紙とデジタル、どちらを選ぶべきか
寒中見舞いは従来「はがき」で送るのが一般的でした。
しかし、近年はデジタルはがきやメール、WEB挨拶状といった新しい手段も法人の間で広がっています。
相手が高齢の経営者であれば紙のはがきが安心ですが、デジタルに慣れた企業相手ならメールやWEB挨拶状が効率的です。
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 紙(はがき) | 形式が整っており信頼感がある | 印刷・郵送のコストや手間がかかる |
| デジタル(メール・WEB) | スピーディーでコスト削減につながる | 相手によっては簡略に見える可能性がある |
大切なのは「どちらが相手に心地よく届くか」を基準に選ぶことです。
寒中見舞いで「年賀状じまい」を伝える方法
法人が「年賀状じまい」を決めた場合、どのように取引先へ伝えればよいのでしょうか。
ここでは、寒中見舞いを活用した伝え方や文例を紹介しながら、スムーズに移行するためのコツを整理します。
最適な時期と伝え方のマナー
年賀状じまいを案内するのは、お正月の華やかな雰囲気が落ち着いた寒中見舞いの時期が最適です。
理由は、年賀状を出さないことを「新年早々に告げる」と相手に寂しい印象を与えかねないためです。
寒中見舞いで伝えることで、「お詫び」と「感謝」をバランスよく表現できます。
| 伝える時期 | メリット |
|---|---|
| 年賀状シーズン前 | 事前告知が可能だが、やや唐突な印象を与える |
| 寒中見舞いの時期 | 落ち着いた時期に案内でき、配慮ある印象を与えやすい |
寒中見舞いは「年賀状じまい」を伝える最も自然なタイミングといえるでしょう。
法人向け文例(理由別:ペーパーレス/SDGs/デジタル移行)
「年賀状じまい」の文面では、一方的に通知するのではなく、相手への感謝と今後の関係継続を明確にすることが重要です。
以下に、法人向けの理由別文例をご紹介します。
| 理由 | 文例 |
|---|---|
| ペーパーレス化 | 「弊社では業務効率化と資源削減の観点から、本年より年賀状でのご挨拶を控えさせていただきます。今後はメール等にてご挨拶申し上げます。」 |
| SDGs推進 | 「弊社は環境保全への取り組みの一環として、年賀状によるご挨拶を終了させていただきます。引き続き変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。」 |
| デジタル移行 | 「このたび弊社では、デジタルでのご挨拶を基本とする方針に変更いたしました。本年より年賀状を失礼いたしますが、今後ともメール等にてよろしくお願い申し上げます。」 |
これらはあくまでひとつの例であり、自社の方針や相手企業の状況に合わせて調整することが大切です。
文例を使う際の注意点
文例は便利ですが、そのまま使うと「形式的すぎる」と感じられることもあります。
法人の場合は、特に「お世話になっている取引先ごとに一文加える」だけで、印象が大きく変わります。
例えば「昨年は共同プロジェクトで多大なるご協力をいただき、誠にありがとうございました」と具体的な事例を添えると、温かみのある挨拶になります。
ポイントは「理由+感謝+今後の関係」を必ずセットで書くことです。
法人の「寒中見舞い・年賀状じまい」実践Q&A
ここでは、法人の担当者が実際に迷いやすい「寒中見舞い」と「年賀状じまい」の疑問をQ&A形式で整理します。
実務にすぐ役立つよう、シンプルかつ具体的に回答していきます。
Q. 年賀状じまい後も寒中見舞いは毎年必要?
必ずしも必要ではありません。
しかし、重要な取引先や親密な顧客に対しては、年に1回の「寒中見舞い」を続けることで関係維持につながると考えられます。
ビジネスにおいて「連絡が途絶える=関係が薄れる」と受け取られがちなので、最低限のご挨拶を続けるのは有効です。
| ケース | 対応 |
|---|---|
| 重要取引先 | 毎年1回は寒中見舞いを送付 |
| 一般的な顧客 | 必要に応じて送付(メールでも可) |
| 一度限りの取引 | 送付不要 |
「誰に送るか」を優先順位で整理することがポイントです。
Q. 寒中見舞いに個人的挨拶は含めてよい?
法人の文書では、プライベート色が強すぎる内容は控えるべきです。
ただし、「今年は新オフィスに移転しました」や「新しいサービスを開始しました」といった業務に関わる近況報告は歓迎されます。
もし担当者個人の挨拶を含める場合は、あくまで会社全体の文面に添える形にしましょう。
Q. 年賀状じまいはメールやWEB挨拶状でもよい?
近年では、メールやWEB挨拶状で年賀状じまいを通知する法人も増えています。
ただし、相手によっては「軽んじられている」と受け取られる可能性もあるため注意が必要です。
特に年代が高い取引先や伝統を重んじる企業には、紙の寒中見舞いを送る方が安心です。
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| メール | スピードが速くコストゼロ | 相手によっては簡略すぎる印象になる |
| WEB挨拶状 | デザイン性が高く柔軟 | リンククリックが必要なため手間がかかる |
| 紙(はがき) | 最も丁寧で安心感がある | コストと手間が発生する |
「相手に合わせた手段を選ぶ」ことが成功のカギです。
法人が寒中見舞い・年賀状じまいを上手に活かすコツ
寒中見舞いや年賀状じまいは、ただの形式的な挨拶ではなく、法人にとって「コミュニケーション戦略の一部」です。
ここでは、実際に企業がうまく活用するためのコツを整理しました。
取引先との関係を損なわない工夫
年賀状じまいを伝える際に重要なのは、相手に「関係を切られた」と思わせないことです。
そのために、「年賀状はやめても、今後のお付き合いは変わりません」というメッセージを必ず添えましょう。
また、年に一度のご挨拶をやめる分、定期的なメールニュースや季節ごとのご案内など、代替手段を積極的に取り入れると効果的です。
| 対応策 | 期待できる効果 |
|---|---|
| 年賀状じまい+寒中見舞い | 丁寧さと配慮を両立できる |
| 定期メールやニュースレター | 接点を失わず関係を維持 |
| SNSでの軽い発信 | 親近感を持ってもらいやすい |
「挨拶をやめる」のではなく「形を変えて続ける」ことが信頼維持のカギです。
社内ルールの周知と統一
法人として年賀状じまいを決める際には、社内ルールを統一して周知することが欠かせません。
担当者ごとに対応がバラバラになると、取引先に混乱を与えてしまいます。
例えば「今年からは寒中見舞いのみ」「来年からはメールで統一」など、全社員が同じ方針で行動できる仕組みを整えましょう。
相手企業への配慮を忘れない
寒中見舞いや年賀状じまいは、あくまで「こちらの都合」であることが多いものです。
そのため、相手の事情や慣習に無理を押し付けないように注意しましょう。
例えば、年賀状文化を重視している取引先に対しては、「今後はメールを中心にご挨拶申し上げますが、ご希望に応じてはがきでも対応いたします」と添えるだけで安心感を与えられます。
| 相手のタイプ | おすすめ対応 |
|---|---|
| 伝統を重んじる企業 | 紙の寒中見舞いを継続 |
| デジタルに積極的な企業 | メールやWEB挨拶状に移行 |
| 長年の重要顧客 | 移行期は両方併用しながら調整 |
「こちらの方針」ではなく「お互いに心地よい形」を探す姿勢が大切です。
まとめ ― 新時代の法人マナーとしての「寒中見舞い」活用
ここまで「年賀状じまい」と「寒中見舞い」について整理してきました。
最後に、法人にとってのポイントをまとめておきましょう。
| テーマ | ポイント |
|---|---|
| 年賀状じまい | コスト削減だけでなく、環境配慮や業務効率化の一環として進んでいる |
| 寒中見舞い | 年賀状に代わる「新しい挨拶ツール」として注目されている |
| 法人マナー | 理由+感謝+今後の関係を必ずセットで伝えることが重要 |
| 実践のコツ | 相手の事情に合わせて紙とデジタルを使い分ける |
「年賀状じまい」は単なる習慣の終了ではなく、新しい時代のビジネスマナーへ進化する過程です。
その中で「寒中見舞い」をうまく活用すれば、相手に対する誠意や気遣いを伝えつつ、企業としての姿勢も示すことができます。
大切なのは「形式」ではなく「相手を思いやる心」です。
今後さらにデジタル化が進むなかでも、この姿勢を忘れなければ、法人の挨拶はより柔軟で価値のあるものになっていくでしょう。
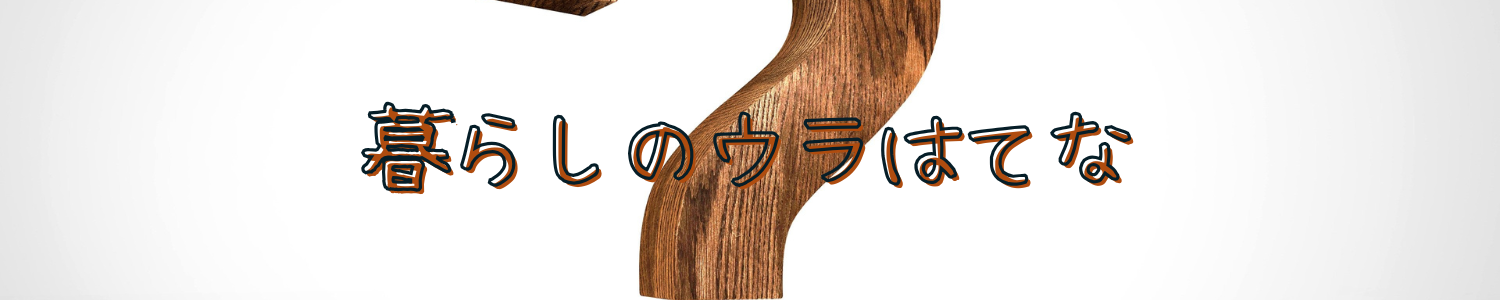
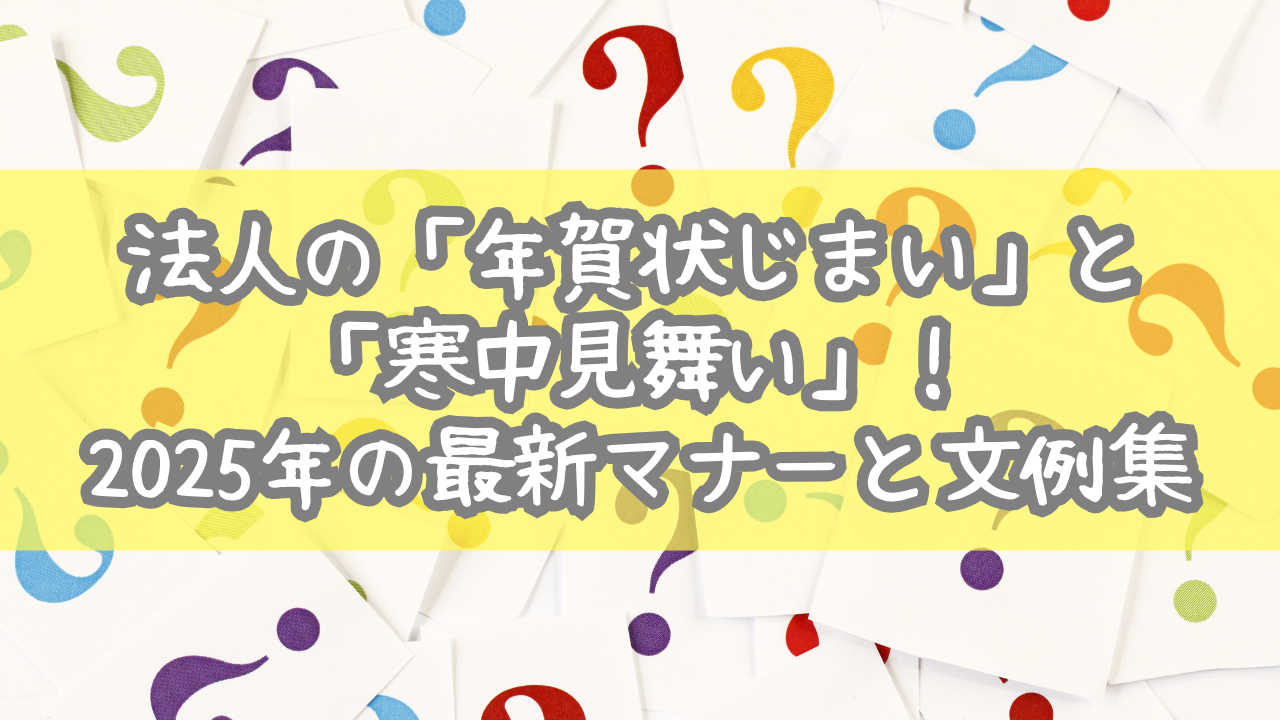
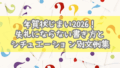
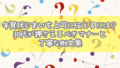
コメント